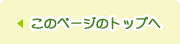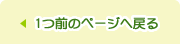教育長ごあいさつ
本村は高知県の最北端に位置した山村で、村の中央を東流する吉野川は、四国の水瓶「早明浦ダム」へと流れ込んでいます。かつては、四国でも有数の銅の鉱山があり、全盛期は4千人を超える人口でしたが、銅の採掘量の減少と早明浦ダムによる水没を起因とする人口流出により、現在では離島を除いて全国で二番目に人口の少ない自治体となっています。
平成17年度には、小学校・中学校同居型の校舎を建築し小中一貫教育を開始しました。義務教育の9年間をトータルで捉え小学校と中学校お互いの教員がすべての児童生徒の成長に責任を持つという考え方を基本に置き、将来の村を担う・支える子ども達の育成に取り組んできました。更に、学校支援地域本部事業、地域学校協働本部事業を導入し、地域ボランティアの方々に学校への支援をいただく中で、村民の想いに応える子ども達を育てるためには、村民の方々にも学校経営に一定の権限と責任を持って参画していただく仕組みが大切との考えに至り、「学校運営協議会」の導入を決め、大川小・中学校を「学校運営協議会設置校」として指定を致しました。現在では、「地域学校協働本部」と「学校運営協議会」を一体化させ「大川小中学校応援団」の名称で、村民の想いが込められた「地域とともにある学校」として運営が行われています。
また、大川村では山村留学にも取り組んでおり、本年で39年目を迎え現在までに延べ315名の「ふるさと留学生」の受入れを行ってきました。村の自然を活用した体験学習を通じて、地元の子どもと山村留学生が一緒になって知的好奇心を高め、意欲的に学ぶことで感性豊かな人間として成長しています。近年では、第二の故郷として帰村し、就職する留学生や、成人式に参加する留学生も増加しています。
令和4年度には、「小中一貫教育」の実践成果や「地域と共にある学校」としての成果を踏まえ、村内で各一校づつの小学校・中学校を廃校し、義務教育学校「大川小中学校」を開校しました。
小さな学校の課題は多くありますが、小さな学校だからこそできる教育の可能性も多くあると考えていますので、新たな取り組みへの挑戦を続けることで、大川村を担い支える人材の育成に努めていきたいと考えています。
令和7年7月
大川村教育長
担当課
- 教育委員会
-
〒781-3721 高知県土佐郡大川村中切16番地4
Tel:0887-84-2449Fax:0887-70-1803